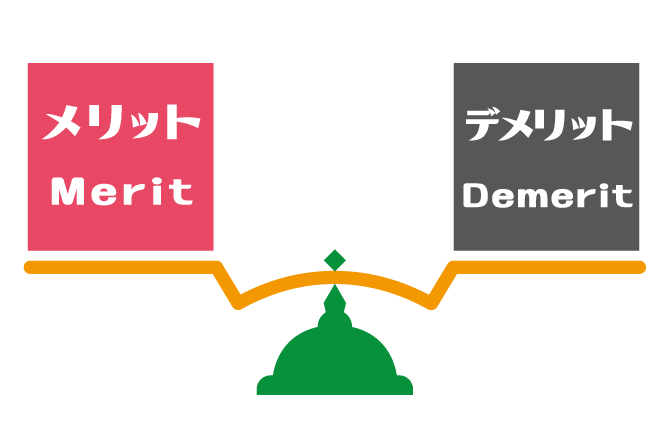本日のコラムでは、複業(副業との違いは後ほど)人材の活用について、起用する企業側の立場でメリットとデメリットを書いてみたいと思います。最初に言っておきますが、当社は複業人材=ミギウデを紹介するサービス事業者なので、基本は、良いことしか言いません。その点は、差し引いてご一読ください。
本題に入る前に、複業と副業の違いについて説明をしておきたいと思います。どっちも一緒だろ!?と思われていると思いますが、当社では意味が違うと捉えています。これもあくまでも当社見解ではありますが、文字の意味から言えば、「副業」とは、本業以外の仕事をして収入を得ることとなります。つまり、メインとサブ(副業)みたいなことと当社では解釈しています。一方、「複業」とは文字の通り、複数の仕事を持つことになります。
「副業」に比べて、「複業」はより多くの収入を得る可能性が高く、かつ多くの時間と労力を必要とし、限りなく本業に近い仕事とも言えます。メイン、サブではなく、全部、メインみたいなイメージで当社は捉えています。当社の解釈で言いますと、本業の空き時間で行われることが多い「副業」に対し、「複業」は本業に限りなく近く、高度な専門性やプロ意識が求められ、複業人材からもアウトプットや成果にもコミットしている状態となります。
当社は、あくまでも複業の方のご紹介を行っております。その点にたって、企業側のメリットとデメリットを以下に記載していきたいと思います。
複業活用のメリット
実際に複業人材を活用する企業様ごとにメリット、デメリットは変わってくるとも思いますが、代表的な内容をいくつか挙げておきたいと思います。
メリットその1: 組織の生産性が上がる
知識と経験のある方が組織内に入ってくるので、間違いなく、組織全体の生産性は向上します。しかし、複業人材を現場の下請けのように指示待ち状態においてしまうと、その生産性は指示する担当者様の能力に委ねられしまいますので、生産性が上がらないケースがありますので、そのような状態はお勧めしません。
経験ある方=自走できる方ではありませんので、複業人材を使って組織の生産性を上げるためには、キチンと複業人材にも稼働スタート時点から目標設定をしておくことが重要です。
メリットその2:組織改革につながる
複業人材が入ってくることによって、結果として柔軟な組織に生まれ変わります。
他社でも十分に活躍してきた優れた人材が組織に入ることで、今までの仕事の進め方や、組織のローカルルールみたいなものに変化が出てきて、組織改革が進みます。
大まかに言って、人間はどうしても「変化」を恐れてしまいます。 その原因は、人間に備わっている「恒常性維持」という本能があるためです。当然に組織内での仕事の進め方にも、こうした“現状維持本能”が働くため、組織内からは、今のままの仕事の進め方でいようとするパワーが働いています。なので、外部からの人材が組織変革には必要なのです。
メリットその3:人材育成につながる
複業人材を入れることで企業は別のコストをかけずに人材育成につなげられます。
これには、いくつかの理由があるのですが、どの組織にでも、外部からの人材には、組織の不満を話しやすいという傾向があります。これは当社の実績でもほぼ全ての取引先様の事例で共通する事象です。こうした不満を聞いてあげて、個々にサポートすることや、または、不満となっている組織内の問題を改善していくことで、急激に人が育つ組織に生まれ変わります。ウソみたいな話ですが、これは本当です。
良いことを3つ述べましたが、次は企業側のデメリットを述べてみたいと思います。
デメリット その1:ノウハウが残らない
複業人材を起用することで、外部から取り入れたノウハウが、複業人材との契約を終了した時点で、ノウハウが企業に残らないというデメリットがあります。
一理はありますが、当社はそのようには思っていません。(デメリットを否定するな!という声が来そうですが、これも正直な当社の考えを書いておきます)
当社は複業人材を起用した場合でも、社内にナレッジはたまっていくと思っています。アウトプットを出してもらうので、それもナレッジとして残りますが、それよりも、契約終了後も、その複業人材とのつながりは残ります。個人的な単なる相談係や、あるいはメンターみたいなことにもなっていきます。複業人材の活用を、社員の教育プログラムとも思っていただいても良いとも思っています。外部から人材が入って、一緒に仕事をするということは、研修ではできないような人材育成の一つの形だとも思っています。
デメリットその2:機密情報の管理コスト
外部から複業人材を入れることで、秘密保持義務や競業避止義務などをどのように管理するかといった、管理コストが発生します。さらに機密情報が漏えいするリスクもあるため、企業は注意しなければなりません。この点は、否定できないところですが、だからこそ、複業人材との契約を法人同士で行う意味もあるとも思っています。責任の所在と管理責任を複業人材の紹介元(当社)にも持たせておくということは保険になるとも思います。
ざっくりとした、メリット、デメリットを記載しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?そもそも、近年の働き方改革の推進や人手不足などにより、複業人材の活用については、今後は、さらに拡大していくでしょう。
だからこそ、正規雇用ではないし・・・業務委託契約が意味不明・・・などと毛嫌いしないで、ちょっとずつでも試してみてはいかがでしょうか?
一番悪いパターンとしては、複業人材の大手企業での経歴や、保有している名刺に数(知り合いの数)だけに期待して、具体的な数字目標もあたえずに、フワッと業務委託契約を結んでしまうのは、絶対にお勧めしません。なんとかアドバイザーとか、なんとかコンサルタントとかというパターンは当社からはお勧めいたしません。
複業人材の活用やその成功事例、失敗事例など、気になることがありましたら、お気軽に当社までお知らせください。当社にも成功例だけではなりません。お客様にご満足をいただけなかった失敗例もあります。その内容も含めて、ご紹介もいたします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
次回は、【複業人材を同じ業界の経験者から選びたがるのは止めたほうが良いです】について書いてみたいと思っています。